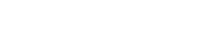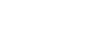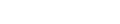晩秋にプラハではじめて、その聖堂の夜間コンサートに聞き入った時間のことを、いまも忘れることができない。10年ほども昔の晩秋、東欧はチェコの首都プラハ。中世にさかのぼる市街地のただなかに、その聖堂はある。聖イジー教会とチェコ語で発音するが、ドイツ語ではリジーと、また英語で綴れば、聖ジョージともよめる。また、同名の由緒ある聖堂も市内にもうひとつある。
さてその日のプラハは、とても寒かった。到着して最初の仕事はといえば、デパートにとびこんで厚手で武骨な毛糸の手袋を入手すること。つぎには、その近傍にある聖イジー教会のコンサートをめざして、その晩のコンサート・チケットを入手すること。
知られるとおり、チェコという国は、第二次世界大戦後に、けわしい辛酸をなめつづけていた。1968年には、ソ連の東欧支配体制に反抗して、自由化をもとめ、「プラハの春」を華やかに演出して、大弾圧を受けた。1989年には、隣国ドイツでの「ベルリンの壁」崩壊によって、「ビロード革命」を。ようやく、ロシアの桎梏(しっこく)から脱して、東欧の自由化の先頭にたった。その市民革命は、いずれも首都プラハの街頭における、市民の叛逆に端を発したもの。じつは、その痕跡は、いまなお聖イジー教会の周辺に、なまなましく残っている。
さらに言えば、聖イジー教会の並びには、ベツレヘム礼拝堂という古い会堂が立つが、じつははるか600年も昔、チェコ(ボヘミア)の信徒たちが、予言者ヤン・フスの激しい教会改革理想の演説に聴き入った場でもある。聖イジー教会は、じつにその長年のプラハ市民の情熱の体温を、現代までもまぢかで感知してきた。
さて、コンサートの開演まで、ちょっと手間どってしまったようだ。ようやく主廊の正面、祭壇を中心として、弦楽器と管楽器の奏者が、10人ほどしずしずと登場する。バロック風の衣装の奏者が、10人ほどしずしずと登場する。バロック風の衣装をまとって、クラシック音楽の雰囲気もたっぷりと演出。数十人の聴衆は、寒々とした聖堂内に着座して、静かに開演を待つ。フレスコバルディやモンテヴェルディの序章から、やがてはバッハにいたる、バロック曲の連続が進行する。すこしずつ、体内が温まってきた。
そこへ、突如として後方の頭上から、巨大な音響が振り落ちてくる。はじめは気づかなかったけれど、正面祭壇のちょうど反対側。10メートル以上もあろう階上に、大柄なオルガンが据え付けられており、そこから満堂にむけて、あの金属音。ほとんど巨大な滝のように、わたしたちの頭上に、束となって振りかかる。その驚き。
さて、このように東欧プラハの聖堂音楽状況を報告してみた。むろん、これは聖イジー教会だけの事情ではない。その首都にも、いくつかの類例がある。西洋古典音楽の故郷というべき都市では、昨今こうした演奏会が人気をよび、聴衆をあつめているという。もちろん観光名所としても。そこでは、事情がよければおなじような経験に遭遇できるにちがいない。
いくつもの楽器から発出されるべつべつの楽音。後陣から降りそそぐオルガンのどでかい爆発音。石造の壁面や石柱に跳ね返ってくる、管楽器の鋭い挑発音。さまざまな楽音が、わたしにむけて落ちてくる。ヨーロッパで古来、人びとが体験してきたように、ロマネスクでもゴシックでも、どんな建造様式であれ、堂内の音はちいさな楽器音でも、人声であっても、重い反響音となって、人の耳に到達したことだろう。聖堂はみな、石造を基本としたのだから、広大な面積と天井高とを体現している。聖イジーのように巨構をほこる聖堂にこそ、その特徴がよく現れているともいえようか。
頭上から降り降りてくるような楽音が、隣席の老女にも。その先の青年にもひとしく共有されていることを、たとえようもない至福と感じとっていた。こんな実感を噛みしめていたのも、じつはかねてから抱いてきた、つぎのような想いをそのとき、あらためて噛みしめていたからである。
わたしたち人間(つまりホモ・サピエンス)は、特有の外界認知の方式をもっているようだ。類人猿からの進化のプロセスで、わたしたち人類は、直立歩行という特別な身体構造と行動方式を獲得した。その結果として、重い大脳をもちはこぶことが、可能となったという。さらには、直立歩行するヒトは、直上や斜めからの情報やら攻撃に対応することが容易となった。動物界のなかでは、さして抜群の身丈をもっていないのに、直立のおかげで、上方や斜め上といった方向での認識や行動の可能域を獲得した。
しかも、同僚のヒトとのあいだで、正面からの対面がふつうとなり、感覚刺激を受け入れるレンジは、ほぼ360度にまで広がった。ひとつひとつの感知能力は、ほかの動物たち、つまり背と腹を上下に向ける動物よりもかなり劣った生物でありながら、ヒトは直立歩行によって、外界をタテ方向からも捉えることが可能となった。ヨコ向き移動する有能な動物たちにあっては、タテ方向への認知や移動が思うに、まかせられなかったのに。
直立歩行するヒトは、いま聖イジー教会の満堂にあふれる楽音を、腹からも背からも、そして加えて頭上からも脚元からも、ひとしく受容することができる。もちろん、その突先は、まずは頭蓋についたふたつの聴覚器、つまり耳に限定されているかにみえるが、じつはたぶん皮膚からも体毛からも、楽音を聴取して、その刺激を体内におくりこみ、蓄蔵しているにちがいない。「腹にしみわたる低音」とか、「肌を撫でるような甘い音」といった比喩は、そんな実体の表現なのかもしれない。
わたしの考えでは、直立歩行のヒトが全身をもって前後や左右、上下からの音を感知する認識能力こそ、じつは「共鳴」力とよぶべきではないだろうか。たんに空気振動の伝達によって、聴覚能力を刺激する波動ばかりか、わたしたちヒトは、身体のいくつもの部分で音波を感受している。直立歩行のおかげで、わたしたちの感受力は、聖堂にしつらえられた石造の天井にも、側壁にも向けられ、ふりそそぎ乱射される楽音を皮膚のなかに取り込むこともできる。
ヒトの身体は、タテとヨコと上下の3次元から楽音を受け取ることで、全身で外界と共鳴する。そして並居る聴衆という多数の共鳴箱は、ついには聖堂をこえて市街地全体を揺るがす音楽につつまれるかのようだ。
話はここで冒頭の主題にもどる。プラハの市民たちの身体は、このしめやかな楽音ばかりではなく、ことによると都市や住居の壁にひびく音響のさまざまを、共鳴音として受容したにちがいない。そしてついには共鳴を求めて発信する「直立歩行」する市民の大群に変身することもあっただろう。
プラハ市中での「プラハの春」合唱も、「ビロード」革命の凱歌も、そして聖イジー教会の外壁に響いたフス派信徒たちの祈りの声も。それらもまた、かつての市中に共鳴音をうながし、そして歴史をこえて、いま21世紀となっても、プラハの音響となって、鳴り響いてくる。終演のあいさつを耳にして、そんな幻想をかみしめながら、わたしは、聖イジー教会の重い扉を押し開けて、プラハの街に歩みでる。モラビア産の赤ワインの杯をもとめて、石畳の道をたどっていくことにしようか。
1941年、東京生まれ。東京大学大学院修士課程修了後、京都大学人文科学研究所助手を経て、1976年から2001年まで、東京大学文学部助教授・教授。のち国立西洋美術館長、ついで2021年まで印刷博物館館長。現在、渋沢栄一記念財団理事長など。専門は、西洋中世史、西洋文化史。おもな著作は『西洋学事始』、『ルネサンスと地中海』、『歴史の歴史』、『ヨーロッパの出現』など。2024年、日本建築学会文化賞を受賞。