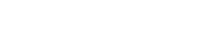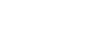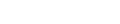「共鳴」とはとても美しい言葉です。私が誰かと共鳴しながら生きていられたら、それはどんなに幸せなことでしょう。そして誰かと誰かが共鳴しあっている姿はとても美しく、私たちに大きな勇気を与えます。
しかし・・・・・・、私はそこにちょっと横やりを入れたくもなります。それはその「共鳴」の内容が美しいものだからなのであって、美しくない「共鳴」もあるのではないでしょうか。例えばネット上で「お金持ちのお年寄りを襲って金を奪おう」という呼びかけがされて、見も知らぬ人間が集まって犯罪を犯す。これもある意味での共鳴に違いありません。ヒトラーに共鳴したナチスの人たちがモーツァルトやベートーヴェンの音楽や西洋古典美術をたしなみながらあのおぞましい虐殺を繰り広げていたというのは有名な歴史的事実です。犯罪者ではないけれど、企業や事業分野を超えて共鳴しあっての共同プロジェクトが結果的には環境や人間関係の破壊をもたらすということも多々あるのです。
となると、単に「共鳴」すればそれでいいのだということにはなりません。共鳴して目標が達成されれば大成功とはとても言えず、その「目標」や「動機」の質が大きな問題になるのです。そしてそのことを考え出すと、問題はものすごく複雑で難しいものとなります。だれかと「共鳴」していて幸せな時に、「これって正しい共鳴なのだろうか」と疑ったりするのはとっても嫌ですよね。しかしそれは私たちにとって避けては通れない問題で、「共鳴」という美しい世界に足を踏み入れるときに、そうした「リテラシー」のあり方が強く問われてくるのです。
共鳴にとってもう一つの大きな問題があります。それは、私は共鳴しているつもりなんだけど相手からは「全然響き合ってない」と思われてしまっているという、悲しい状況です。
私は今年の3月まで28年間在籍した東京工業大学で、研究指導や講義の他に、全学部の学生が参加できる全学ゼミも担当していました。各自が自由なテーマで発表してそれを全員で議論するというとても自由なゼミです。そしてこの10年あまりは私がリレー講義を担当していた慶應義塾大学看護医療学部の学生も加わってのゼミとなっていました。
そこで数年前、二年続けて看護の学生から東工大の学生たちに向かって同じような内容の発言がありました。「あなたたちは人間らしくない」「人間とロボットの違いが分かってない」「話してるととても傷つく」・・・・・・。
そのきっかけは「ワークライフバランス」をテーマにした発表でした。
この発表は「看護師をやりながらどのような人生を歩んで行くべきか」について考察したものでした。彼女たちの多くが先端の病院で看護師として仕事をしますが、そこでは非常に高度な技術と知識を求められ、いったん就職すると、なかなか辞めるに辞められないという現実があります。その一方で、結婚や出産で一旦辞めると、今度は現場を離れたブランクを埋めるのが難しい。日進月歩の高度医療の世界でついていけなくなるかもしれない、若い後輩たちからオバサン扱いされてしまうかもしれないといった不安を感じていて、彼女たちの悩みは尽きません。
ゼミ仲間のその人生の悩みを聞いて、東工大の男子学生は異常にヒートアップし、いつもに増して活発な議論が展開されました。一度職場を辞めた人が戻ってきたときのリカレント教育のシステムはこうしたほうがいいとか、病院の勤務システムや給与システムを変えたらいいのではとか、いろいろな考察、提案がなされていきました。でも東工大の学生が熱く議論すればするほど、看護学生たちは沈黙していきました。しかしゼミ生の半数が沈黙していることに気づかず、男子学生たちは熱く議論し続けます・・・・・・。
そして数週間後のゼミ合宿である女子学生がぽつりとこんなことを言いました。「こんなにディスカッションをするゼミは他にないと思います。きっと人間が好きな人たちが集まっているのだろうと思って参加したのですが、東工大の人たちがこんなに人間に興味がないということにビックリしました」。そして他の看護学生も大きくうなずいたのです。これには東工大生たちもびっくりでした。そして私もびっくりしました。東工大という理系の大学の中で、このゼミ生たちは明らかに人間に興味があり、好奇心のある学生たちだったからです。
何がいけなかったのでしょうか。思い返してみれば、ワークライフバランスの発表の時、東工大生が議論していたのは全部「システム」の話でした。システムを改善すれば問題が解決するに違いない・・・・・・。給与、勤務時間、リカレント教育のシス前に将来の働き方と生き方にとても悩んでいる同級生がいて、声を発している」という事実からは遠くなっていきました。「ぼくがもし君のパートナーだったら」とか「キャリアと子育ての両立にぼくは何ができるか」とか、当事者としてどうするかという話をする学生は一人もおらず、「共鳴」して話しているつもりが、「全然共鳴しない人たち」と思われてしまったのです。
苦しんでいる人がそこにいるのに、その苦しみに寄り添い、苦しみを引き受けていっしょに考えるという姿勢や発想がまるでなかった・・・、東工大ゼミ生にとってはとても苦い体験になりました。そしてゼミ生が全員入れ替わっての次年度のゼミでもまったく同じような発言がなされたのも、なかなかショックな体験でした。そもそも看護学部では患者さんの苦しみに寄り添うという言葉が入学以来数千回も繰り返されるのですが、東工大生に「寄り添うって言葉聞いたことある?」と聞くと、「入学以来いちども大学で聞いたことはありません」と断言しますので、そもそも「文化」がまったく違うのですが。
東京工業大学では2012年にリベラルアーツセンターを創設し、2016年にリベラルアーツ研究教育院を創設し、大胆なリベラルアーツ教育改革を開始しましたが、いま振り返ってみると改革に10年以上関わり、創設からの院長も6年務めた私自身、ゼミでの慶應看護学生からのキツイ一言も改革の大きな後押しになっているような気がしています。私自身が中高6年間は男子校で、大学は理科系で入学したのですが、大学で女子学生とお話をしていて、「○○ちゃんの話はこういうことだよね」と要約すると、「上田君、私の話聞いてたけど何を聞いてたの?全然違うよ」と言われた個人的な苦い思い出も重なっているのかもしれませんが。
「共鳴」を語るとき、その素晴らしさ、それが生みだす創造性と喜びを語るのはもちろんですが、何が共鳴を妨げているのか、共鳴という思い込みの暴力となっていないか・・・・・・等のネガティブ要因も考えていかなければいけません。学問分野や事業分野にはどれもある種の「癖」があります。それは物の考え方の癖とも言えるし、世界をそもそもどう捉えているかという世界観の「癖」でもあります。そして人間ひとりひとりにももちろんその人なりの「癖」があります。その「癖」に気づくことなく、その思考パターンや行動パターンで「良かれ」と思ったことをしても、他の人たちには全然通じないどころか、暴力的な行為だと捉えられてしまうこともあることに気づくことが肝要になります。
日本の大学では、1990年代初頭から「大学は役に立つことをやれ」「即戦力を生みだせ」という圧力が高まり、教養教育が後退し、専門教育を特化する動きが顕著になりました。ただその時代が20年あまり続いてから、そうしたひとつのディシプリンに特化した「即戦力」の人たちが、想定外の出来事が次々と起こり、新たな地球課題や倫理的な問題が生じてくる世界で、イノベーティブな働きができないことが明らかになってきて、リベラルアーツ教育の復権という流れとなってきました。リベラルアーツとは「リベラル」「アーツ」つまり自由になる技、自由にする技という意味ですが、これはギリシャ・ローマ時代の二つの階級、「自由市民」と「奴隷」のうち、自由市民が持つべき素養のことです。「教養」から「リベラルアーツ」に言葉が変化した背景には、現代社会で私たちがほんとうに「自由」行くべきか」について考察したものでした。彼女たちの多くが先端の病院で看護師として仕事をしますが、そこでは非常に高度な技術と知識を求められ、いったん就職すると、なかなか辞めるに辞められないという現実があります。その一方で、結婚や出産で一旦辞めると、 今度は現場を離れたブランクを埋めるのが難しい。日進月歩の高度医療の世界でついていけなくなるかもしれない、若い後輩たちからオバサン扱いされてしまうかもしれないといった不安を感じていて、彼女たちの悩みは尽きません。
ゼミ仲間のその人生の悩みを聞いて、東工大の男子学生は異常にヒートアップし、いつもに増して活発な議論が展開されました。一度職場を辞めた人が戻ってきたときのリカレント教育のシステムはこうしたほうがいいとか、病院の勤務システムや給与システムを変えたらいいのではとか、いろいろな考察、提案がなされていきました。でも東工大の学生が熱く議論すればするほど、看護学生たちは沈黙していきました。しかしゼミ生の半数が沈黙していることに気づかず、男子学生たちは熱く議論し続けます・・・・・・。
そして数週間後のゼミ合宿である女子学生がぽつりとこんなことを言いました。「こんなにディスカッションをするゼミは他にないと思います。きっと人間が好きな人たちが集まっているのだろうと思って参加したのですが、東工大の人たちがこんなに人間に興味がないということにビックリしました」。そして他の看護学生も大きくうなずいたのです。これには東工大生たちもびっくりでした。そして私もびっくりしました。東工大という理系の大学の中で、このゼミ生たちは明らかに人間に興味があり、好奇心のある学生たちだったからです。
何がいけなかったのでしょうか。思い返してみれば、ワークライフバランスの発表の時、東工大生が議論していたのは全部「システム」の話でした。システムを改善すれば問題が解決するに違いない・・・・・・。給与、勤務時間、リカレント教育のシステムの改善・・・・・・、ただそれを議論すればするほど、「いま目の前に将来の働き方と生き方にとても悩んでいる同級生がいて、声を発している」という事実からは遠くなっていきました。「ぼくがもし君のパートナーだったら」とか「キャリアと子育ての両立にぼくは何ができるか」とか、当事者としてどうするかという話をする学生は一人もおらず、「共鳴」して話しているつもりが、「全然共鳴しない人たち」と思われてしまったのです。
苦しんでいる人がそこにいるのに、その苦しみに寄り添い、苦しみを引き受けていっしょに考えるという姿勢や発想がまるでなかった・・・・・・、東工大ゼミ生にとってはとても苦い体験になりました。そしてゼミ生が全員入れ替わっての次年度のゼミでもまったく同じような発言がなされたのも、なかなかショックな体験でした。そもそも看護学部では患者さんの苦しみに寄り添うという言葉が入学以来数千回も繰り返されるのですが、東工大生に「寄り添うって言葉聞いたことある?」と聞くと、「入学以来いちども大学で聞いたことはありません」と断言しますので、そもそも「文化」がまったく違うのですが。
東京工業大学では2012年にリベラルアーツセンターを創設し、2016年にリベラルアーツ研究教育院を創設し、大胆なリベラルアーツ教育改革を開始しましたが、いま振り返ってみると改革に10年以上関わり、創設からの院長も6年務めた私自身、ゼミでの慶應看護学生からのキツイ一言も改革の大きな後押しになっているような気がしています。私自身が中高6年間は男子校で、大学は理科系で入学したのですが、大学で女子学生とお話をしていて、「○○ちゃんの話はこういうことだよね」と要約すると、「上田君、私の話聞いてたけど何を聞いてたの?全然違うよ」と言われた個人的な苦い思い出も重なっているのかもしれませんが。
「共鳴」を語るとき、その素晴らしさ、それが生みだす創造性と喜びを語るのはもちろんですが、何が共鳴を妨げているのか、共鳴という思い込みの暴力となっていないか・・・・・・等のネガティブ要因も考えていかなければいけません。学問分野や事業分野にはどれもある種の「癖」があります。それは物の考え方の癖とも言えるし、世界をそもそもどう捉えているかという世界観の「癖」でもあります。そして人間ひとりひとりにももちろんその人なりの「癖」があります。その「癖」に気づくことなく、その思考パターンや行動パターンで「良かれ」と思ったことをしても、他の人たちには全然通じないどころか、暴力的な行為だと捉えられてしまうこともあることに気づくことが肝要になります。
日本の大学では、1990年代初頭から「大学は役に立つことをやれ」「即戦力を生みだせ」という圧力が高まり、教養教育が後退し、専門教育を特化する動きが顕著になりました。ただその時代が20年あまり続いてから、そうしたひとつのディシプリンに特化した「即戦力」の人たちが、想定外の出来事が次々と起こり、新たな地球課題や倫理的な問題が生じてくる世界で、イノベーティブな働きができないことが明らかになってきて、リベラルアーツ教育の復権という流れとなってきました。リベラルアーツとは「リベラル」「アーツ」つまり自由になる技、自由にする技という意味ですが、これはギリシャ・ローマ時代の二つの階級、「自由市民」と「奴隷」のうち、自由市民が持つべき素養のことです。「教養」から「リベラルアーツ」に言葉が変化した背景には、現代社会で私たちがほんとうに「自由」なのかという問いがあります。お金が儲かればいい、自分の利得が最大限になればいいといった平板な価値感にとらわれてしまった私たちはほんとうに「自由市民」なのか、自らを拘束する「癖」にがんじがらめの「奴隷」なのではないかという問い返しがあります。
リベラルアーツについてこのところ大きな企業からの講演のご依頼が増えてきました。事情をうかがってみると、リベラルアーツが軽視され「即戦力」として入社した人たちが管理職になる年齢となったものの、いま「自分の軸」は何なのかに悩んでいるという背景があるようです。自分なりの軸、人生哲学、世界の見方がない人は管理職となっても部下に「ひたすら業績を上げろ」としか言えず、魅力的なリーダーにもなれません。そして創発的なイノベーションを生む環境も作れません。そこでもう一回リベラルアーツから人生を見直そうという動きが広まりつつあるのです。
それは自分の癖や弱みを知り、逆に自分の強みは何なのかを知ることでもあります。かつてのゼミを思い返してみて、もし東工大のゼミ生が自分たちの「寄り添う文化」の不在に気づいていて、だからこそそこで自覚的にきちんと苦しみに寄り添い、それに加えて「ぼくたちの強みはシステムの改善にあるんです!」と言って議論していれば、看護学生の人たちも自分たちの強みと癖にも気づくことができて、そこには「共鳴」が生みだされていたのではと思うのです。
神の恵みのように降ってくる「共鳴」の奇蹟もあります。そして自分の限界や思いに気づき、それを他者とすり合わせながら得られていく「共鳴」もあります。考えてみれば、そうやって新しい自分へと脱皮しながら得られる「共鳴」も、やはり私たちが生きていく中で得られる奇蹟のような体験なのではないでしょうか。
1958年東京都生まれ。東京大学教養学部、大学院総合文化研究科博士課程修了、医学博士(岡山大学)。
86年よりスリランカで「悪魔払い」のフィールドワークを行い、文化人類学の立場から「癒やし」を提唱。主要紙の論壇時評を担当、テレビコメンテータも務める。1996年~2024年在職の東京工業大学においては、リベラルアーツ研究教育院を創設して初代院長になり、その後副学長に就任。
主な著書に、『生きる意味』、『立て直す力』、『かけがえのない人間』、『目覚めよ仏教!―ダライ・ラマとの対話』、『とがったリーダーを育てる-東工大「リベラルアーツ教育」10年の軌跡』他。